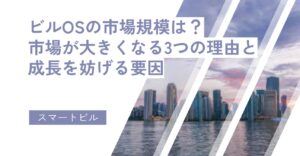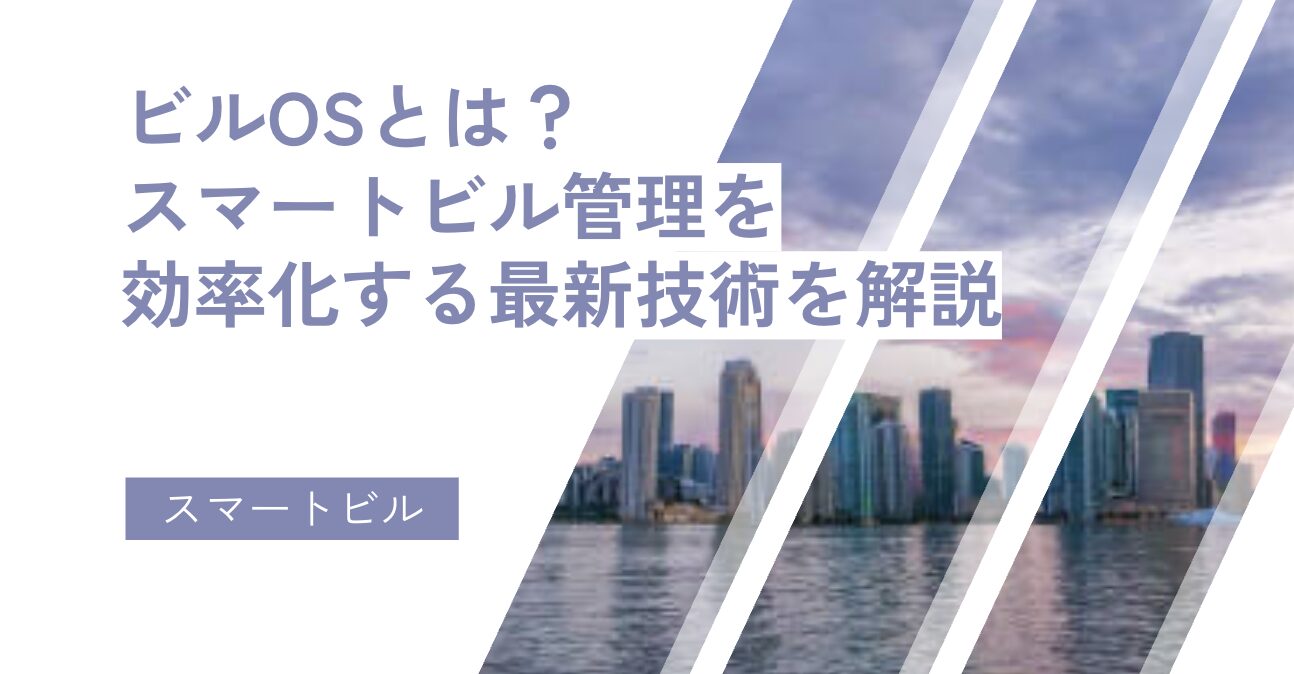「スマートビルディングにビルOSが必要なの?」
「ビルOSを取り入れるメリットは?」
このような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。
ビルOSはビル管理を効率化し、省エネルギーや設備の自動制御を可能にする最新技術です。しかし、具体的にどういうものなのか、機能やメリットについて疑問を持つ方も多いでしょう。
そこで本記事では、ビルOSの仕組みや、データ構造、導入すると得られるメリットを解説します。
この記事を読むと、ビルOSがビル管理で果たす役割を理解できます。ぜひ最後までお読みいただき、導入の参考にしてください。
ビル管理の必要性

ビル管理の必要性を理解すると「ビルOS」の役割や利点を、より深く理解できます。
ビル運営におけるエネルギーコスト削減や環境負荷軽減の重要性を知ると、持続可能なスマートビル管理への道筋が見えてくるでしょう。
ビル管理の重要性が高まっている要因は、主に以下の3つです。
- ビル運営にかかる費用の増加
- ビル管理の複雑化
- 環境負荷への対応
経済産業省によると、オフィスビルの消費電力の約72%を空調と照明で占めており、これらの費用を管理することは、ビルオーナーにとって重要な課題です。
ビル運営にかかる費用はエネルギー価格の上昇や設備の老朽化による更新費用の増大で年々増加しており、効率的なエネルギー管理がますます求められています。
また、ビルにはエレベーター・空調システム・セキュリティシステムなど、異なるメーカーの多彩な設備があります。
これらの設備を一元的に管理するためには、各設備に合わせた適切なメンテナンスや運転スケジュールの最適化などの運用が必要です。
しかし、それは非常に手間のかかる仕事です。さらに、地球温暖化の進行にともなってCo2排出量の削減も求められています。
ビルは空調設備や照明で大量の電力を使用するため、エネルギー起源のCo2排出量が増加しやすいです。
費用管理・設備管理・環境対策といった問題に対応するため、エネルギー効率の高い設備の導入や再生可能エネルギーの活用など、環境に配慮したビル運営が必要となっています。
ビルOSとは

ビルOSとは、Building Operating Systemの略称です。
ビル設備に関連するデータを収集・蓄積・連携する機能を備えた「データ連携基盤」のことです。
ビルOSには、3つの主要な機能があります。
- ビル設備と外部システム間の通信仕様の違いを吸収し、相互の連携を可能にする
- ビル設備から取得したデータを最適な状態で蓄積・管理する
- ビル設備と外部システム間でデータの送受信を可能にする
たとえば、ビルOSを取り入れていないビルでは、エレベーターや空調・照明がそれぞれバラバラに稼働しています。
しかし、ビルOSを取り入れると、設備を一元管理できます。異なるメーカーの設備でも、ビルOSが通信仕様の差異を吸収するためです。
ビルOSは温度や湿度・電力使用量など、ビル内のデータを収集し、分析しやすい形で保存します。このデータをもとに設備の状態を把握し、効率的な運用が行えます。
さらに、ビル設備と外部システム間の連携も可能にするため、空調の最適な制御やロボットの効率的な運用が実現するでしょう。
つまり、ビルOSはビル全体をスマートに管理するための基盤となるソフトウェアです。これによりエネルギー効率の向上や、快適な室内環境の維持、設備の効率的な運用が可能となります。
ビルの維持管理に必要なビルOSのデータ構造

ビルの維持管理にはビルOSのデータ構造を把握することが欠かせません。
建物を管理するためのデータを整理・区分し、管理や運用を効率化するための基盤のこと
本章ではビルOSの代表的なデータ構造を、3つご紹介します。
- Real Estate Core
- Brick Schema
- W3C Building Topology Ontology
上記のデータ構造を理解すると、ビルOSがどのように情報を整理し、活用しているかがわかります。
一つひとつ解説していきます。
1. Real Estate Core
Real Estate Core(リアルエステートコア)は、建物の持ち主や管理する人が、建物に関する情報を簡単に共有できるようにするためのデータ構造です。
主に以下のような情報を管理します。
| 建物情報 | 建物の名称・所在地・建築年など |
|---|---|
| 資産情報 | 建物内の設備・家具・備品・耐用年数など |
| 空間情報 | 各部屋の設備・面積・配置など |
Real Estate Coreの活用方法の事例は以下の通りです。
たとえば「建物A」の空調設備が古くなったとします。
建物Aのオーナーは設備管理会社に点検の連絡をしますが、そのときにReal Estate Coreがあると、過去のメンテナンスを確認可能です。
そうすると、オーナーと設備管理会社は過去の点検結果を確認しながら修繕できるのです。
2. Brick Schema
Brick Schema(ブリックスキーマ)は、建物の中の機械やセンサーを管理するためのデータ構造です。
主に以下のような情報を扱います。
| 場所情報 | センサーや機器が設置されている場所の情報 |
|---|---|
| 装置情報 | 空調・照明・エレベーターなどの制御装置の情報 |
| 監視ポイント情報 | 各設備から取得できるデータの情報 |
Brick Schemaを使うと、ビル内の設備に取り付けたセンサーの測定記録が管理できるようになります。
管理したデータの有効活用にもつながるでしょう。
3. W3C Building Topology Ontology
W3C Building Topology Ontology(ダブリューサンシー ビルディング トポロジー オントロジー)は、建物の中の空間を管理するためのデータ構造です。
主に以下のような情報を整理します。
| 敷地情報 | 建物が立地する土地の特性や周辺環境 |
|---|---|
| 建物情報 | 建物全体の構造や特徴 |
| 階情報 | 各階の構成や特徴 |
| 空間情報 | 部屋や廊下などの詳細な空間データ |
このデータ構造を使うと、建物内の空間を細かく把握することが可能です。
たとえば、多くの人が行き交う駅前の便利な場所に、会社が所有している土地があるとします。(敷地情報)
その土地には、会社が建てた大きなビルがあり(建物情報)、3階には社員が働く事務所があります。(階情報)
この事務所に設置された空調設備を定期的に点検します。(空間情報)
このように、建物の場所から具体的な部屋や設備に至るまでの情報を段階的に絞り込むことで、必要なエリアや設備を見つけだし、効率的な管理が可能になります。
ビルOSの主要機能
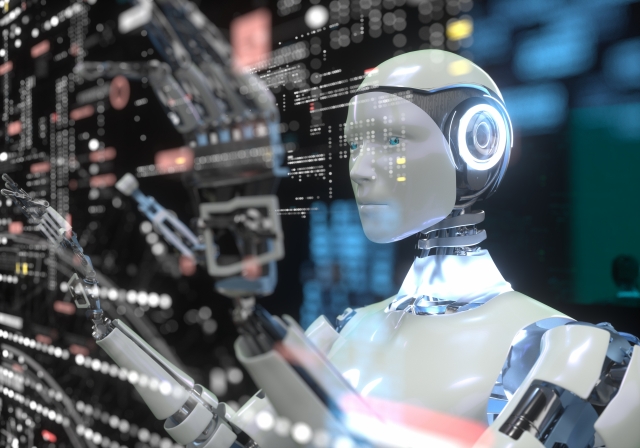
ビルOSの主要機能を表にまとめました。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| エネルギー管理 | 照明や空調などの電気使用量をリアルタイムで把握し最適化する |
| セキュリティシステム | 入退室管理・監視カメラ・異常検知などを一元管理する |
| 空調・照明の自動制御 | 在室状況や外部環境に応じて、空調や照明を自動で調整する |
| 設備メンテナンス予測 | 設備の稼働データを分析し、故障や不具合を事前に予測する |
| ロボットの連携 | 清掃ロボットや警備ロボットなどと連携し、業務を自動化する |
これらの機能により、ビルの運営効率は大幅に向上し、テナントや利用者の満足度も高まります。
たとえば、エネルギー管理機能を使えば、電気の使用量が多い時間帯や場所を特定し、無駄な消費を抑える施策を練ることが可能です。
また、セキュリティシステムを一元管理すると、不審者の侵入をいち早く察知し迅速な対応を取れるようになります。
このように、ビルOSは単なる管理ツールではなく、ビルの価値を高め、運営を効率化する強力なパートナーとなるのです。
ビルOSを取り入れた事例

ビルOSを取り入れた事例を2つご紹介します。
- ビルコミ|竹中工務店
- 鹿島スマートBM|鹿島建設株式会社
ビルOSの活用例をチェックすると、その効果や可能性がより具体的に理解できます。
それでは見ていきましょう。
ビルコミ|竹中工務店
竹中工務店が開発した「ビルコミ」は、ビルのさまざまな情報をクラウド上で一元管理できるビルOSです。
ビルコミの特徴は、以下の通りです。
- ビル内の各種センサーからデータをリアルタイムで収集し、分析する
- 収集したデータをAIが分析し、空調や照明を自動制御する
- ロボットを活用し、設備管理・警備・清掃などの業務生産性の向上を図る
ビルコミを導入した「竹中セントラルビル サウス」では、全面改修によりCo2排出量50%削減を実現予定です。
鹿島スマートBM|鹿島建設株式会社
鹿島建設株式会社は日本マイクロソフト株式会社と連携し、建物管理プラットフォーム「鹿島スマートBM」を開発しました。
鹿島スマートBMは、BEMSやIoTで取得したデータを自動的にクラウドへ収集・蓄積します。そしてAIに学習させ、エネルギーの消費予測や設備機器の異常を検知するシステムです。
BEMS:ビルで使用する電力の使用量を可視化し、設備を制御する管理システム
IoT:モノをインターネットに接続し、相互に情報を交換するシステム
これにより、以下のことを実現します。
- 機器の異常や故障の早期把握
- 過去情報に基づく作業や行動支援による管理の省人化、高度化
- 省エネルギー支援によるランニングコスト削減
鹿島スマートBMは、鹿島が保有する建物や管理する建物など、国内の多くのビルで運用されています。
ビルOSの導入ステップ

ビルOSの導入は、ビル管理の効率化や最適化を実現するための重要なプロセスです。
ここでは、ビルOSを導入する際の基本的なステップを解説します。
| 1 | 各システムの導入 | 温度センサーや人感センサー・カメラなどを設置する |
|---|---|---|
| 2 | システム・設備間の連携調整 | 導入したシステムの既存の設備をビルOS上で連携させる |
| 3 | 連動テストの実施 | 各システムのデータが正しく送受信できているか、ビルOSで適切に制御できているかを確認する |
| 4 | 実際の運用を開始 | 運用データを蓄積・分析し、さらなる最適化を図る |
また、ビルOSの大きな利点の一つは、複数のビルを一元管理できることです。他拠点をクラウドで接続すると、多棟管理が可能となります。
これにより、企業全体での管理効率化やコスト削減が実現できるでしょう。
まとめ

この記事では、ビルOSの仕組みや、データ構造、導入すると得られるメリットを解説しました。
ビルOSはビルの価値を高め、競争力を強化する戦略的な投資となる可能性があります。ビルOSの導入を検討する際は、自社のニーズや課題を明確にし、適切なソリューションを選択することが重要です。
株式会社メンテルでは、スマートビルディング実現をサポートするアプリケーションやソフトウェアを開発しています。
ビル管理の効率化と省エネルギーを実現したい方は、ぜひ株式会社メンテルのホームページをご覧ください。