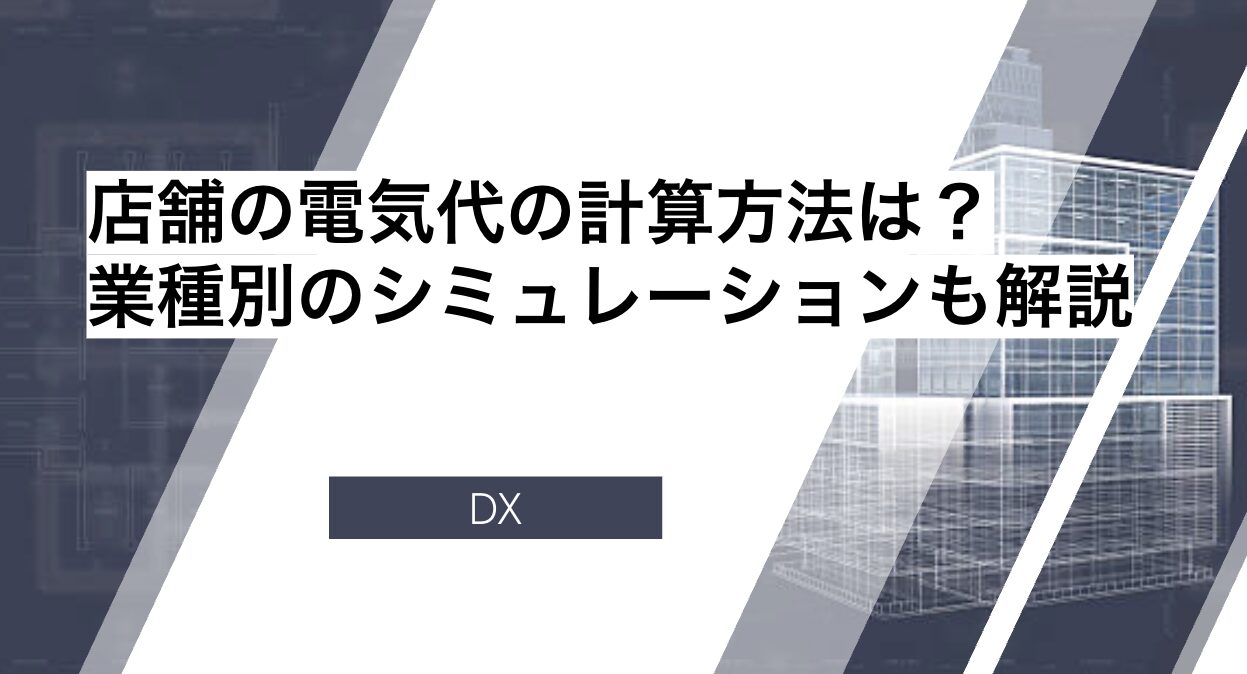近年の猛暑による電力需要の上昇や天然ガスの価格高騰などにより、電気代は値上がりし続けています。
店舗の経費を圧迫させないためには、電気代の仕組みや計算方法を把握して、何に電気が使われているのか把握することが重要です。
電気代の仕組みがわかると、節約するための施策を打てます。本記事では、店舗の電気代の仕組みや計算、節約の方法などについて数字を用いて解説します。
店舗ビジネスを営んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。
店舗の電気代の相場
店舗の電気代の相場は、売上100万円あたり3〜5%だとされています。
しかし、一概には言えません。また、新電力ネットによると、店舗の電気代については以下のような調査結果が出ています。
| 電力購入量 | 売上高100万円あたりの電気代 | |
|---|---|---|
| 飲食料品小売業 | 37,779 | 15,827円 |
| 飲食店 | 23,330 | 24,838円 |
飲食料品小売業は、大型スーパーや24時間営業のコンビニなどを含むため、電力の購入量は飲食店より多くなっています。
しかし、その分売上も大きいため、売上高100万円あたりの電力利用料は1.5%ほどです。飲食店は、電力購入量に比べて売上高が少ないため、電気代の負担が大きくなっています。
上記から店舗の電気代はおおむね5%以下だと言えるでしょう。飲食店の電気代を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
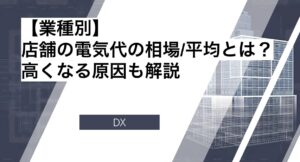
店舗の電気代の計算方法の仕組み

電気料金の計算式は、以下の要素で構成されています。
電気料金 = 基本料金 + 電力量料金 + 再生可能エネルギー発電促進賦課金
しかし、電気料金を構成する各要素が具体的にどのようなものなのかわからない方も多いでしょう。
そこで本章では、以下の3つについて紹介します。
- 基本料金
- 電力量料金
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ひとつずつ見て行きましょう。
基本料金
基本料金とは、電力会社の契約プランに応じて毎月支払う固定料金です。
その計算式は以下の通りです。
基本料金 = 料金単価 × 契約電力 ×(185 – 力率)/100
料金単価は契約電力量1kWあたりの単価を指します。契約電力量の単価は、電力会社ごとに異なります。
契約電力は、店舗が毎月使用できる電力量の上限のことです。規模に応じて「低圧」と「高圧」「特別高圧」の3つに分けられます。
力率は、供給された電力のうち、実際に有効に利用されている電力の割合のことです。力率が高いほど割引が大きくなり、基本料金が安くなります。一方、力率が低いと、電気料金は割高になります。
つまり(185 – 力率)/100 =(力率割引 × 割増)と計算することが可能です。
基準値は85%です。この数値を超えると基本料金が割引され、下回ると割増しされます。
たとえば、割引がない力率85%の場合は、(185 – 85)/100 = 1です。力率100%の場合は、(185 – 100)/100 = 0.85となり、15%割増になります。。
参考:東京電力エナジーパートナー|業務用電力(契約電力500kW未満)
電力量料金
電力量料金は、実際に利用した電力量に応じて毎月発生する費用です。
以下の計算式で算出されます。
電力量料金 = 電力量料金単価 × 使用電力量 + 燃料費等調整額
電力量料金単価は1kWhあたりの単価のことです。「夏季」と「その他季」で料金が異なり、電力需要の高い「夏季」のほうが単価が高くなります。
燃料費等調整額は、平均燃料価格の変動により、毎月加算または差し引かれる調整額のことです。燃料費調整単価と1ヶ月間の電気使用量を掛けて算出されます。
燃料費等調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の電気使用量
燃料費調整単価は、過去3ヶ月間の平均燃料価格を基に決まり、3ヶ月後の電気料金に反映されます。
参考:東京電力エナジーパートナー|燃料費調整のお知らせ(2024年11月分)
再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は、再生可能エネルギーの普及を促進するために設けられた制度です。
賦課金単価は、関西電力や東京電力では2023年度まで1kWhあたり1.40円でしたが、2024年度には1kWhあたり3.49円へ値上げされました。
環境省によると、2030年ごろまでは、再エネ賦課金は増加し続ける見通しです。
- 2023年度:1.40円/kWh
- 2024年度:3.49円/kWh
3種類の契約電力の違い

基本料金を計算するには、低圧と高圧、特別高圧の3種類の契約電力を理解する必要があります。
まず契約電力は、以下のように決められています。
| 契約種別 | 内容 |
|---|---|
| 低圧 | 供給電力:100〜200V 契約電力が50kW未満で、一般家庭や店舗などに向いている |
| 高圧 | 供給電力:6kV 契約電力が50kW以上で大型商業施設やオフィスビル、学校などに向いている |
| 特別高圧 | 供給電力:20,000V以上 契約電力が2,000kW以上で大規模工場や鉄塔などに使用する |
主に建物の規模によって契約電力を決めることになります。コンビニやレストランなどの店舗を経営するならば、低圧を契約するのが一般的です。
電力料金は電力会社によって異なりますが、契約電力が大きくなるほど、単価が安くなる傾向にあります。
店舗の電気代の計算シミュレーション

これまでに解説してきた計算方法を基に、電気料金のシミュレーションを紹介していきます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金と燃料費等調整額は実際の数字を使用しています。
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金:3.49円/kWh
- 燃料費等調整額:-8.67円/kWh
契約電力は30kW(低圧)と仮定して、基本料金と電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課については東京電力エナジーパートナーのデータを参考にしています。
| 基本料金 | 1155円84銭 /kW |
|---|---|
| 電力量料金 | 25円57銭/kWh |
| 力率 | 85% |
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 3.49円/kWh |
| 低圧契約の契約電力数 | 30kW |
| 燃料費等調整額 | -8.67円/kWh |
参考:東京電力エナジーパートナー|賦課金等について
参考:東京電力パワーグリッド|燃料費調整単価および燃料費等調整単価のお知らせ
本章では飲食店と小売店の電気代について、それぞれ数字を当てはめてシミュレーションしていきます。
飲食店
飲食店の形態には、ファミリーレストランや居酒屋などがあります。
飲食店では、食材の加熱調理や冷蔵保存が必要なため電気代が多くかかります。
農林水産省のデータを参考に例を上げると、居酒屋の年間電気使用量は277,799kWです。おおよそ月に23,000kWとなります。
これを計算式に当てはめると以下の通りです。
- 基本料金 = 1155円 × 30kW × (185 – 85)/100 = 34,650円
- 電力量料金 = 25円/kWh × 23,000kW +(-8.67円/kWh × 23,000kW) = 375,590円
- 電気料金 = 34,650円 + 375,590円 +(3.49円/kWh × 23,000kW) = 490,510円
飲食店の1ヶ月の電気代は490,510円となりました。
小売店
小売店には、コンビニエンスストアや大規模なスーパーなどさまざまな形態があります。
ここでは24時間営業のコンビニエンスストアを例にシミュレーションします。
東京都環境局によると、コンビニエンスストアの電気使用量は、年間173,000kWです。1ヶ月当たりだと約14,000kWです。
また、飲食店と条件を揃えるため、低圧電力で30kWの契約として計算します。計算式は以下のとおりです。
- 基本料金 = 1155円 × 30kW × (185-85)/100 = 34,650円
- 電力量料金 = 25円/kWh × 14,000kW + (-8.67円/kWh × 14,000kW) = 228,620円
- 電気料金 = 34,650円 + 228,620円 + (3.49円/kWh × 14,000kW) = 312,130円
コンビニエンスストアの1ヶ月の電気代は、312,130円となりました。
店舗の電気代を節約する方法

店舗の電気代を節約する方法として最適な手段は、契約電力を見直すことです。
たとえば、店舗の電力が「低圧」で、契約電力が30kWのところを20kWにすると、電気代を節約できます。
そのため、店舗運営に影響が出ない程度に電力消費量を減らし、それに見合う契約内容に変更することが重要です。
毎月の電力消費量を減らす手段としては、主に以下が挙げられます。
- 照明をLEDに変更する
- 空調の稼働を最適化させる
- 冷蔵・冷凍庫の開け閉めを減らす
上記のような手段で節電を行い、電力消費量が減ってから、契約電力を見直しましょう。
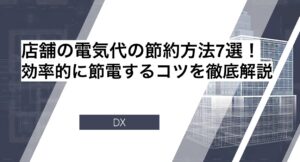
まとめ
この記事では、店舗の電気代の計算方法について解説しました。
店舗の電気代は地域や電力会社、規模、種類によって異なります。しかし、エネルギー使用量が増える季節や営業時間が長い店舗では、毎月の電気代が大きな負担になるでしょう。
複数の店舗を経営している場合は、AIやIoTを活用したシステムを導入することで、効率的に電力を使用できます。
株式会社メンテルでは、複数店舗の電力消費を一元管理ができるシステムの開発をサポートしています。店舗運営に携わる担当者様は、お気軽にご相談ください。