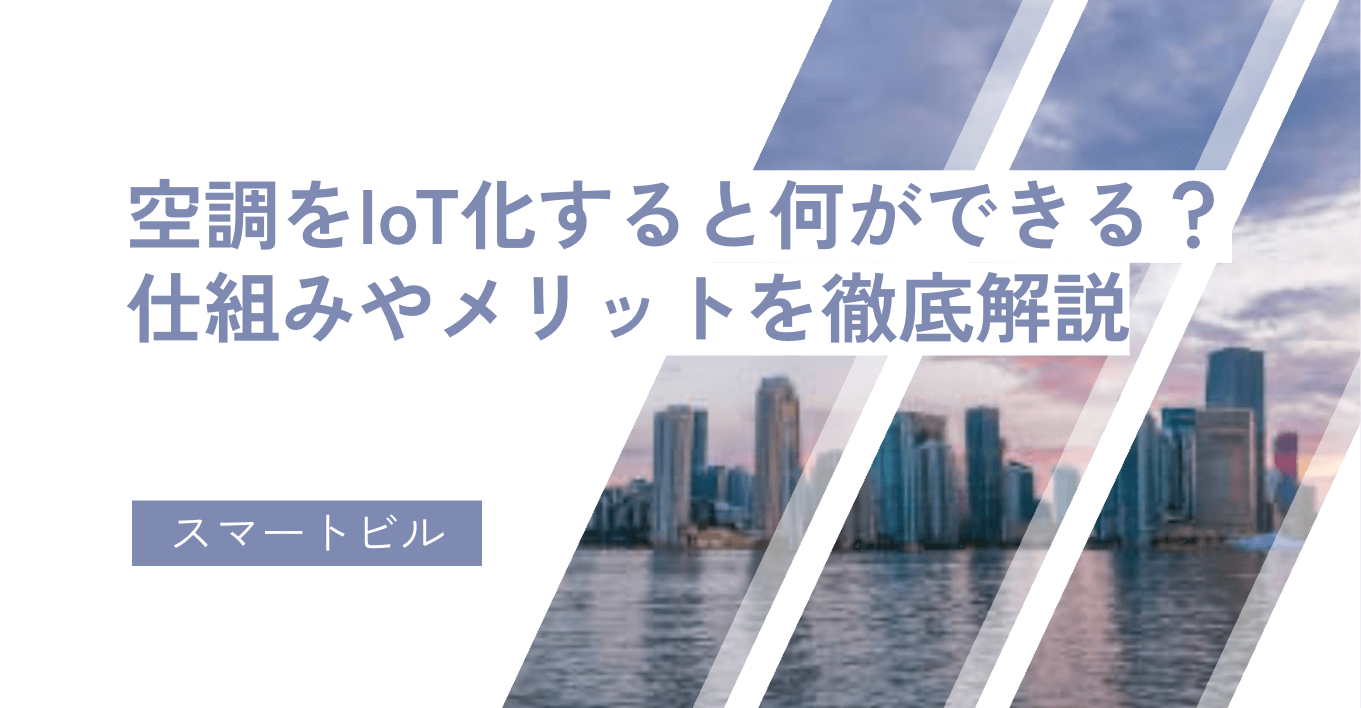IoTとは、家電製品や産業用機器などの「モノ」と「インターネット」をつなぐ技術です。
IoTを活用すれば、複数ビルの空調を一元管理でき、運用コストを削減できます。
本記事では、空調のIoTの仕組みやメリット・デメリット、成功事例などを解説します。
空調のIoT化すると、どのくらい空調管理の負担やコストが減るのかわかるため、ぜひ最後までお読みください。
空調のIoTの仕組み
IoTとは「Internet of Things」の略で、空調やテレビ、冷蔵庫、産業用機器などをインターネットにつないで、データを収集し管理・共有・分析する技術です。
空調のIoTの仕組みは以下のとおりです。
- IoTセンサーが室温や湿度などのデータを収集
- データをインターネットに送信
- 中央管理システムでデータをグラフに変換
- 空調設備に指示して稼働状況を最適化
空調をIoT化すれば、リアルタイムで稼働状況や消費エネルギーなどのデータを収集できます。
また、特定の部屋の空調を停止したり、温度調整したりすることも可能です。
IoT化は、設備にIoTセンサーを組み込んでインターネットに接続することで実現可能です。
空調をIoT化する4つのメリット
空調をIoT化するメリットは次の4つです。
- 遠隔操作により外出先からも効率的な管理ができる
- 消費電力を可視化し無駄な稼働を削減できる
- 使用状況を学習し自動で最適な運転ができる
- 温度制御と自動運転によりコストを削減できる
ひとつずつ見ていきましょう。
1. 遠隔操作により外出先からも効率的な管理ができる
空調をIoT化すれば、スマートフォンやタブレットで遠隔操作や一元管理ができます。
従来、複数のビルを管理している運営会社は、設定の変更やトラブルに対応するため、各ビルへ巡回する必要があるかと思います。
しかし、すべてのビルをIoT化して通信環境を整えれば、本社から複数拠点の空調を遠隔で管理・操作することが可能です。
その結果、ビルの管理会社は巡回や現地対応の負担を大幅に軽減できます。
2. 消費電力を可視化し無駄な稼働を削減できる
IoT化すると消費電力をリアルタイムで「見える化」できます。
施設管理者は時間帯や設備別のエネルギー消費量を把握できるため、無駄な稼働やピーク時の空調負荷を特定できます。
そして無駄な稼働を停止・抑制すると、空調を最適に運用でき、省エネにつながるビル運営が可能となるでしょう。
空調のIoT化で、環境や経営にも配慮したビル運営ができるようになります。
3. 使用状況を学習し自動で最適な運転ができる
AIが搭載されたIoTシステムは、入退館や熱源のデータをもとに、時間帯ごとの利用状況を学習・予測し、自動で空調の稼働を最適化させます。
たとえば、月曜日の朝に出社人数が多いことを検知し学習すると、始業前に冷房を自動で開始します。
一方、ノー残業デーには、就業時刻より遅く帰る人がいないのを把握して、帰宅時間にあわせて段階的に出力を低減させることが可能です。
使用状況に沿って電源を自動的にON/OFFできるため、無駄なエネルギーをできるだけ使用しないビル運営ができます。
なお、AIを使って空調を最適化させた仕組みについては、次の記事でわかりやすく解説しております。

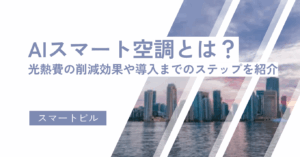
4. 温度制御と自動運転によりコストを削減できる
IoT化された空調は、人が快適と感じる室温に設定温度を自動調整し、過度な冷暖房を防ぎます。
これにより無駄なエネルギー消費を抑制でき、光熱費を削減できます。
環境省によれば、エアコンの設定温度を1℃調整することで、消費電力量を冷房時に約13%、暖房時に約10%削減可能です。
また、24時間365日の自動運転と遠隔監視により、空調の管理にかかる作業の手間を大幅に省けます。
その結果、施設管理者の人件費も削減でき、経営の安定化にもつながります。なお、空調の省エネ方法は次の記事で解説しておりますので、あわせてお読みください。

空調をIoT化する2つのデメリット
空調をIoT化するデメリットは以下の2つです。
- 通信機器が故障すると空調の管理・監視が困難になる
- 停電により機能が停止する恐れがある
詳しく見ていきましょう。
1. 通信機器が故障すると空調の管理・監視が困難になる
IoTは通信機器に依存した技術であるため、機器に不具合が生じると、空調を適切に管理・監視できず、運転が停止する恐れがあります。
通信機器が故障するリスクに備えて、以下の2つの対策が必要です。
- 定期的なメンテナンス
- バックアップ体制の確保
月に1回はメンテナンスを行い、劣化やバグがないか確認してください。
また、バックアップしておけば、通信機器が故障した際にすべてのシステムがダウンするのを回避できます。
適切な対策を講じると、リスクを最小限に抑えられるでしょう。
2. 停電により機能が停止する恐れがある
IoT化した空調を会社のパソコンで管理している場合、停電が発生した際にすべての機能が停止する恐れがあります。
対策は施設全体をカバーする非常用発電機を使用して、停電下でもパソコンを使えるようにすることです。
停電時でもIoTデバイスへの電力供給を止めないことが、IoTを活用するうえで非常に重要です。
空調のIoT化による成功事例
空調のIoT化による成功事例を2つ紹介します。
- 竹中工務店|AI×IoTの活用で空調消費エネルギーを年間26%削減
- 日立システムズ|IoTを活用した自動制御により使用電力43%削減
事例を参考にIoT化された空調を取り入れた際のイメージを明確にしてみてください。
竹中工務店|AI×IoTの活用で空調消費エネルギーを年間26%削減
竹中工務店では、AI×IoTを活用したスマートビルの取り組みにより、空調の年間消費エネルギーを従来施設と比較して26%削減しました。
竹中工務店が導入した技術的なアプローチは、以下のとおりです。
- エリアごとの人数をセンシングして、外気導入量を最適化
- 来館者の増加が予測される日は、オフピーク時に外気導入を行い、ピーク時の負担を軽減
- 画像認識AIで服装や年代、性別を解析し、室温・湿度・放射温度・風速・着衣量・活動量の6要素を最適化
- 年齢・性別構成に応じて、冷媒蒸発温度を制御しエネルギー使用量を削減
これらの取り組みの結果、来訪者へのアンケート調査では、冬期・中間期・夏期いずれも回答者の90%以上から「快適」「不満がない」との評価を獲得できました。
竹中工務店は、AI×IoTの活用で運用エネルギーの削減や快適性の向上を実現した事例といえるでしょう。
参考:AI・IoTを活用した運用エネルギーの削減 – 竹中のデザイン|竹中工務店
日立システムズ|IoTを活用した自動制御により使用電力43%削減
家電量販店を展開する株式会社ノジマは、日立システムズのIoTを活用した自動制御により、2011年比で使用電力を43%削減しました。
日立システムズの導入内容は、次のとおりです。
- クラウド上のエネルギー管理システムが、インターネット経由で各店舗の空調設備の電源や設定温度をコントロール
- 店舗内の2〜8台の温度センサーが室温を計測し、店内が常に快適な状態に保たれるよう自動制御
- 本社で空調運転を集中管理し、店舗スタッフは手動操作が不要
- 営業時間外は空調を自動で停止させ、無駄な冷暖房を防止
これにより快適な店舗環境を維持しながら、省エネと電力コストの大幅な削減を実現しました。快適性を維持しながら大幅なコスト削減を達成できた成功事例といえます。
参考:エネルギーマネジメントサービス導入事例:株式会社ノジマ様:株式会社日立システムズ
空調をIoT化するまでの流れ7ステップ
空調をIoT化するには、以下の7つのステップを踏む必要があります。
- 空調の使用状況を分析する
- 収集したデータの活用方法を明確にする
- 施設にあったシステムを設計する
- IoTデバイスを空調に設置する
- データ収集と管理ができる状態にする
- テストを行う
- 実際の運用を行う
まずは空調の使用状況を分析し、エネルギーの消費パターンや運用効率を把握しましょう。次に収集したデータをもとに、施設に合ったシステムを設計します。
そしてIoTデバイスを空調システムに設置し、データの収集と管理が可能な状況にしてください。テストを数回行ったのち、実際に運用を開始します。
施設の規模や取り付け箇所によって異なるものの、導入決定から運用開始まで3ヶ月以上かかると想定しておきましょう。
空調をIoT化する際の費用
空調をIoT化する際の費用は、建物の規模や空調の設置台数により、ばらつきがあります。
実際に提供されているサービスの一例を紹介します。
| 商品名 | 会社名 | 料金 |
|---|---|---|
| おまかSave-Air® | 関西電力株式会社 | 月額39,800円~ |
| P-AIMS | パナソニック株式会社 | 100万円~ |
| エナジーセーバー | アイリスオーヤマ株式会社 | 要問い合わせ |
資金の用意が難しい場合は、月額制サービスがおすすめです。料金がホームページに掲載されていない場合は、各会社に問い合わせて確認しましょう。
空調をIoT化する際の注意点
空調をIoT化する際の注意点は以下のとおりです。
- 導入に労力がかかる
- 建物の規模によっては導入コストが高額になる
- サイバー攻撃を受ける可能性がある
IoT化された空調の導入には、ある程度費用がかかります。
しかし、効率的な自動運転により、今までかかっていた無駄な消費電力を抑えられるため、長期的に見ると初期費用の回収も可能です。
また、インターネットに接続するため、サイバー攻撃を受ける可能性もあります。空調をIoT化する場合、セキュリティ対策は必須です。
空調のIoT化に関するよくある質問
空調のIoT化に関するよくある質問をまとめました。
- IoTが普及しない理由は何ですか?
- 空調を後付けでIoT化できますか?
IoT化について疑問点があれば、ぜひ参考にしてください。
IoTが普及しない理由は何ですか?
総務省の調査によると、IoTが普及しない理由は以下のとおりです。
- 導入すべきシステムやサービスがわからないから(46.0%)
- 使いこなす人材がいないから(43.7%)
- 導入後のビジネスモデルが不明確だから(39.7%)
- 導入コスト・運用コストがかかるから(33.0%)
- 導入に必要な通信インフラ等が不十分だから(14.2%)
- 利活用や導入に関する法令などの整備が不十分だから(4.4%)
空調のIoT化に興味があるものの、導入に迷っている方は専門家への相談がおすすめです。
メンテナンスや使用方法の相談などアフターフォローが充実している業者を選ぶことが、導入成功のポイントです。
参考:総務省|令和2年版 情報通信白書|企業におけるIoT・AI等のシステム・サービスの導入・利用状況
空調を後付けでIoT化できますか?
空調を後付けでIoT化することは可能です。センサーや指示を実行するための機材を取り付けて、インターネットに接続すればIoT化できます。
しかし、専門的な知識が必要であるため、自社の社員だけで空調を後付けでIoT化するのは難しいでしょう。
空調を後付けでIoT化したい場合、IoTを扱う企業へ問い合わせることをおすすめします。
まとめ|AI×IoTによる空調の省エネ化ならばメンテルにお任せください
空調のIoT化により、外出先からの遠隔操作や消費電力の可視化ができます。
手動で行っていた分析や調整が自動化できるため、企業は業務を効率化させられるでしょう。
株式会社メンテルは、ビルや商業施設などの空調サービスを提供しています。IoT×AI×環境シミュレーションを駆使して、空調の省エネ化が可能です。
IoT空調の導入を検討している場合は、ぜひ一度メンテルにご相談ください。